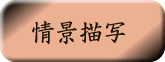
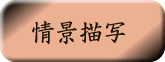
| 2002年の「情景描写」 | 「忍耐と寛容」(6) 祭 8/4 | 「忍耐と寛容」(5) 会話 7/14 | |
| 「忍耐と寛容」(4) 買い物 6/23 | 「忍耐と寛容」(3) 刻一刻 6/14 | 「忍耐と寛容」(2) 閃光 6/3 | 「忍耐と寛容」(1)マスクの下 5/18 |
| ホームレス 2/10 | 築地再訪 1/20 | 遠い呼び声 1/9 | バトル・ロワイアル 1/3 |
| 2001年の「情景描写」 | 写真の少女 12/24 | あの日 11/28 | 笑顔の女達 11/17 |
| ラ・フランス 11/11 | 転倒 11/6 | 美しい老い 10/26 | 初体験 10/18 |
| 別れ 10/14 | リバイバル 10/11 | 見える目 10/10 | 「情景描写」開設に寄せて 10/6 |
|
動悸が速くなっているのだけは確かだった。不安とか怖れとか、期待とか歓喜とか、名前の付く感情は何一つなかった。よく人が地に足が着かない感じと言ったり、どこをどう歩いてそこに至ったのか記憶にないなどというのを聞いたことはある。一瞬の宇宙遊泳、無意識の恍惚。その時「あ、ジュピターだ」と思った。病院の一階ホールに微かに鳴り響いているバックグラウンドミュージックは確かにモーツァルトの交響曲「ジュピター」だった。二十数年前、結婚披露宴の最後にあの曲を選んだ。 私は築地に眼科の診察を受けに来ていた。前回、瞼のひどい腫れを見て眼科医に「再発かも知れない」と無造作に言われ、MRIの結果が出てからもう一度と予約してあったのだ。どんなにステロイド系の点眼液をさしても腫れは収まらず、殊に毎朝起き抜けの顔は我ながら別人のようだと思っていたので、再発を宣告されても驚かないつもりだった。だから呼ばれて診察室に入り、コンピュータ画面を盛んにクリックしながら断層写真を眺める医師の前で、覚悟に似たものは付いていた。それが、「今のところ、病巣の拡がっている形跡はありませんね。」と言われてむしろ拍子抜けしたといってもいい。
「は、あの、では、化学療法に入る件は・・・。」 九月は遙か遠い将来のように思えた。毎週毎週、明けても暮れても築地通いの半年余りだったのに、一ヶ月以上もお暇をもらえるなんて。何が何だか分からないまま、私は会計カウンターに向かって歩いたというわけだ。窓口の事務員が、重症患者にも執行猶予付きで一時解放される患者にも全く態度を変えずに接するのが不思議な気がした。会計表を渡して支払窓口に呼ばれるまでの僅かな合間に、ジュピターが私の全身を照らした。 病院の外は真夏日。正午の太陽が高い。さて、真っ直ぐ帰るかそれとも久しぶりに少し歩いてみようか。この暑さの中を歩き回るのは尋常ではない。でもほんの少しだけなら。今まで何ヶ月も、たとえ外がどんなに良い季候であろうと、歩きたいと思いもしなかった。体力の温存の為にとにかく早く帰って体を休めるか、消耗の少ないうちに次の目的地へ行くかという判断しか選択肢になかった。歩くといっても、どこへ行こう。ふっと川向こうのことが思い浮かんだ。いつぞやまだ寒い頃、隅田川の岸辺を歩きながら対岸にいつか渡ってみようと思ったっけ。でもいつそんな気持ちが湧くか分からないな、と自分に言い聞かせた記憶が蘇る。そうだ、月島にでも行ってみよう。多分、今を逃すと「その時」は永遠にめぐってこない。私は川に向かって歩き出した。 勝鬨橋を対岸まで渡りきるのは初めてのこと。いつも手前をウロウロしていた。昔開閉したのはこのあたりかしら、などと中央にさしかかった時足を踏みならしてみたり、きらめく水面を眺めたり、橋の上の気分はいつも特別だ。隅田川縁の小学校の屋上に立派な時計台があるのに気付いた。橋を渡らなければ一生知らずにいた時計。空が青い。夏の青は特に深い。前に見た地図を思い出しながら、見当だけ付けて月島方面に歩く。表通りには陰らしきものが殆どない。帽子をかぶっていて良かった。同僚達に「この季節で良かったわね」とよく言われる。「帽子をかぶっていてもおかしくないわよ」と。頭髪を失ったところを隠すための帽子だと知っている人の目には痛ましく見えたのか、あるいは私の格好はどこか異様だったのかも知れない。だが、この頃他の人の目は殆ど気にならなくなっている。比較ではないのだ。私は、私。生きていればそれでいい。 程なくさしかかったのは、隅田川と朝潮運河を繋ぐ「月島川」。その名も「月島橋」の欄干にもたれて、しばらくあたりを眺める。えんじ色の水門、係留された釣り船、岸辺の柳が風に揺れ、その下で釣り糸をたれる人の影。一つ向こうの橋の上を時折車が行き来する。川風はあるんだかないんだか、こう日が高くちゃかなわない。名物もんじゃ焼きの店でも探して腹ごしらえしながら涼もうか。そう思い直してカンカン照りの商店街に踏み込んだもの、人影はまばら。商店と商店の間にある路地を覗くと、そこだけ陰が濃い。一度は路地裏のもんじゃ焼き屋の前にたってみたものの、普通の家のようで、どこが入り口だか遂に分からなかった。 表通りに戻り、思い切って一軒の店の扉を開けると、主が顔を上げた。
「いらっしゃい、何か。」 ははあ、商売より祭、か。がらんとした通りを渡って私は向かい側の店に入った。昼下がり、この熱いのに鉄板をジュウジュウいわせながら何組かの客がもんじゃ焼きを食べている。ソースの焦げる匂いが鼻を突く。「お一人さん」と声がかかって、私は小さなテーブルについた。出された冷水が美味しい。もんじゃ焼きなんて普通は一人で食べるものじゃない。つつき合って食べるところが美味いのだろう。だが、常識は常識。人にはそれぞれ事情がある。本日はこれが私の祝い膳。たとえ執行猶予付きでも。紅ショウガ入りのもんじゃは、辛かった。せめて餅やチーズでも入れたのを頼めば良かった。でも後の祭り。汗をかきかき小ベラですくって一人黙々と食べるもんじゃ焼き。それもまたよしとしよう。 地下鉄の駅に吸い込まれるまで、私はまたぶらぶらと商店街を歩いた。アーケードには観光用に三角屋根がついていて、小綺麗だけれどもどこか気取ってこの町にはそぐわない。雑然とした裏路地の方がこの町らしい。だが、余所者にそこの事情なんか分かるものか。祭提灯の赤がくっきりと青空に映えて、夏本番。いつまた病院に呼び戻されるか分からない。でもとりあえず、翌週の血液内科と放射線科の診察で「逆転判決」が出ない限り、ひとまず私は一月以上のお暇をもらえた。今はそのことだけ考えて、放流された魚の気分でいればよいのだと、私はその瞬間を大事に胸の中で握りしめていた。 川に架かった橋を渡ると、見知らぬ町へたどり着く。思い切って渡らなくては行けないところがそこにある。病院へ通わなければ、来られなかった町かも知れない。さまよい歩く私の心が、病気と一緒にひとときゆるむ。まつりばやしが聞こえるようだ。
「月島界隈」の写真はこちらをクリックしてご覧下さい。 |
|
1/20(日), 2002
|
|
築地は卸売市場でもっとも名の知られた街だ。あらゆる種類の食品が取り引きされる、東京の、いやおそらく日本の食品ビジネスの中枢と言えるだろう。観光名所にもなっている。とりわけ海外からの訪問者の関心を引き、早朝の競りを見物に行く人々が大勢いると聞く。近接する銀座の洗練とは趣を異にする東京の相貌を、築地は見せてくれる。
その街の真ん中に、国立がんセンターがある。最新鋭の設備を誇る病院の真新しいビルは、辺りを威圧して聳えている。私は暫し口をぽかんと開けてその偉容を見上げた。かつて私の知っていた建物とは似ても似つかない。ちょうど六年前、私は何度もここを訪れたものだ。当時父が肺ガンで死にかけていた。あのときの陰鬱な病院はどこへかき消えたのだろう。あの建物を息詰まる痛みとともに思い出す。 最初に会った若い医師は家族・係累にガンに罹った者がいるかどうか尋ねた。「父と二人の叔父が」と答えてから「手の施しようがないと言われて、父はこの病院を追い出された後、ホスピスで亡くなりました」と私は一気に付け足した。医師は僅かに眉を上げて「そうですか」と答えた。ボスに会わせる前に彼が私に手渡したのは、検査や手術を受けた場合、生体摘出組織やデータを研究用に提供することへの同意書だった。「将来のガン研究推進のために、是非ご協力をお願いしたいと思います」と、医師は慇懃に言う。それは些か奇妙な申し出のような気がした。なぜなら私は未だガンと診断されたわけではないのだ。国立がんセンターを訪れたのは、どこよりも精密な検査が受けられるからという地元の病院のすすめによるものだったはず。これではまるで、がんセンターの門をくぐる人間はすべて役に立つ研究材料と見なされるも同然ではないか。書類を私はよほど胡散臭い目で見ていたに違いない。医師は慌てて拒否権もあることを強調した。私は不承不承、書類を受け取った。 六年前には、よもや自分がこの病院へ診察を受けに来ることになるとは思わなかった。父の苦しみを全身で受け止めてはいたけれど、その病気は自分とは無縁だと思っていた気がする。だから地元のクリニックの眼科医が、「国立がんセンター」へ行って専門医の精密検査を受けたらどうですと言いだしたときには、ぎょっとした。病院の名前自体が禍々しい。「ガン」は「エイズ」と同様、人の心に特殊な魔力を持つ。私は単純素朴に抵抗と恐怖の態度を露わにしたらしい。数ヶ月通った公立病院に決別し、長引く眼疾についてのセカンドオピニオンを求めた医師は、笑いながら私の恐慌状態をいなしてこう言った。 「心配要りませんよ。落ち着いて考えてください。複雑な症例を数多く手がけている専門医の診察を受けるのは合理的なことだと思いませんか。素人医者がいくら診ても埒があかないんなら、あれこれ思い煩うより築地に行って確定診断を出してもらってらっしゃい。もし僕があなただったらそうするな。今ここで電話して予約を取ってあげますから。いいですね。」こうまで言われたらとても「結構です」とは言い出せない。がんセンター詣でをすることになったのは、このようなことの次第による。 新米患者とはいえ、初診の時に何もかも明らかになるわけもないことくらい、私にももう分かっていた。思った通り、初日には、大病院の各階を上がったり降りたりしながら幾つかの検査予約を取ることで精一杯。検査その一は来週、その二は翌週、もう一つは三週目、等々。(それでも自然に順番待ちしていたら五月初旬になってしまうはずの検査を、主治医が「至急」のマークで今月中にしてくれたものもある。各部署が緊密にオンラインで繋がっているのは見事だった。)様々なチェックポイントで認証を受けたり、採血されたり、「服はここに脱いでください。大きく息を吸い込んでー、はい、終わりです」と、突然X線撮影をされたり、検尿コップを手渡されたり、目まぐるしいオリエンテーリングのようだった。あっちで待たされこっちで足止めされ、有に半日、私は巨大な新ピカの病院で過ごした。初めこそ緊張していたものの、次第に気分は緩んできて、いつしか病院の流れに乗せられていた。その世界にはそこの決まりがあり、言語がある。こちらが自意識に固まっていても何の意味もない。私はただの患者だ。それ以上でも以下でもない。私がどこの誰か、何をしている人間なのかは問題ではない。その組織の中を動く列車に飛び乗るだけだ。ただ、緊急の場合はいつでも飛び降りる覚悟さえしていればよい。必要と判断したら、自分で「降りる」選択の余地はある。(実際私はこの前まで乗っていた列車を黙って飛び降りた。何一つ解決せず空しく費やした時間とエネルギー。) 繰り返される検査、集められるデータ、分析、診断、そして治療。それは長い行程だ。いい加減うんざりしてくる。ただ、この経験を通じて可能なのは、医療機関の内側を観察すること。権威ある病院と言われる場所の実態を私はじっくり見るつもりでいる。同時に自分の内面をも。「老・病・死」を逃れられる人はいない。生きている限りそれについて書くことは可能だろう。やってみようと思う。 迷宮の中で、私はエスカレーターもエレベーターも見つけられなくなる瞬間があった。そばを通る白衣の女性に尋ねてみると、彼女は「関係者以外立ち入り禁止」と書いてある扉をまっすぐ指さして言った。「この中にエレベーターがあります。上の階へ行く時私はいつもここを利用しています。」私は微笑みながら礼を言い、躊躇わず示された扉を開けて中へ入っていった。患者は他へ行けと私に言う人は誰もいなかった。面を上げて背筋を伸ばし「関係者」のような顔をすると、私の気後れは消えた。患者だからとおどおどする必要がどこにあるだろうか。権威に怖じけずくことはない。病名にも。 「国立がんセンター」は、無数の生活と心情を持つ個々人の患者に奉仕するためにあるのではなかったか。そうだ、私も無名の患者候補生の一人だが、実際の病名が何と付くにしろ、誇りもあれば自尊心もある。再訪した築地はもっとも根本的な自己証明を私に思い出させた。恐れる理由は何もない。
|
|
12/24(月), 2001
|
|
過日、私は東京・表参道の「ミズ・クレヨンハウス」を訪ねた。ここは基本的には「女、子どものための本屋」だ。様々な本ばかりでなく、化学物質を使わない化粧品、自然素材の雑貨、有機栽培の食品なども売っている。もちろん「男、大人」を排除しようというのではなく、広義のフェミニズムとマイノリティーに関心を持つ人なら誰が訪れても興味深い場所と言える。おしゃれな街の一角にぴったり収まる素敵な店。
アフガニスタンの子どもたちと女性たちの写真を見ることが、今回の訪問の主な目的だった。店の階段の壁を地下一階から三階まで使った、実に質素な写真展。「ミズ・クレヨンハウス」へは「女性と現代」というクラスの学生たちと共に、見学会として出かけた。学生たちは教室の四角い空間から解き放たれて、ウキウキしていた。それは私も同じ。川崎けい子という女性写真家の作品群に、私たちは大いに感銘を受けた。 百点余りあるパネルの中でも私が特に強い印象を受けたのは、熱暑の野外で煉瓦作りをする十代の少女の写真だった。彼女はすり切れた服を着て、裸足だった。薄い胸の前でかすかに両手を組み、バケツの傍らに一人で立っている。モシャモシャの髪の毛がほっそりした顔を取り巻き、彼女は倦んだ様子で虚空を見ている。諦念としかいいようのない表情の他、何かを訴えているようにも見えない顔つきをしている。きっと十代も始めの少女だと思う。どんなに大きくても14歳に満たないだろう。けれども彼女はとても「女らしい」。彼女の姿態には優美さがある。彼女の顔には強ささえ漂う。そんなにも幼いのに、彼女は女であることの意味を知っているように見えた。 その少女はまだブルカを着る年には達していない。パキスタンのアフガン人難民キャンプに住まわせられている。故郷を遠く離れ、彼女の家族は最も抑圧され、最も収奪された生活を余儀なくされている。写真の少女は、運命に従っていた。そのような重荷を背負いながら、それでも彼女はおそらく年長の者達から受け継いだとおぼしき人間の尊厳とたおやかさを備えている。私はその写真の前を長い間離れられなかった。 何の発言もしないけれど、裸足のアフガン少女は大地に立ち、おのれの存在を世界に向かって主張していた。見てご覧、誰も彼女の命を奪うことは出来ない。見てご覧、彼女の命は彼女のものだ。誰も彼女に触れることは出来ない。自由は尊厳と深く結びついている。私は彼女の自尊心を見たように思った。無言のうちに彼女は「私は誰のものでもない」と言っている。 一枚のアフガン少女の写真に導かれ、私は 「アフガン女性革命協会(RAWA)」のウェッブサイトへたどり着いた。これは驚くべき情報量を誇るサイトだということがすぐ分かった。まだその膨大な資料の一部を読み始めたに過ぎないが、未知の世界に関する優れたアーカイヴなのは明らかだった。そのサイトから発信する女性たちは、私に自分自身を振り返るよう促す。「抑圧され収奪された」人々の底力を感じる。彼女たちと向き合っていると、私は自分が次に踏み出す一歩について寡黙にならざるを得ない。少なくとも多弁は無用だろう。
|
|
11/17(土), 2001
長い巻き布のターバンで頭を覆った男達の写真はいくらでも見るけれど、最近のアフガン情勢を伝える新聞紙上に、ブルカというあの目の周りだけ編み目の窓を開けた、全身をすっぽり覆う布で包まれた姿以外の女達を目にすることは滅多になかった。北部同盟がタリバンをカブールから撤退させたと報じられた日の新聞第一面を、ブルカを脱ぎ、含羞を帯びた笑顔の女性のカラー写真が飾った。これが解放の象徴だとでも言いたげに。彼女は疑わしげでもあるが、自由を希求していることは明らかだった。眉間にはまだ苦悩の皺が刻まれている。それでも尚、彼女の瞳は明るい眉の下で輝いている。こんなにも美しい人がブルカの中にいるのだった。
|
別の写真には手放しで笑う二人が写っていた。説明には「タリバンに強制されていたブルカの着用から五年ぶりに解放されて喜ぶ女性達」とある。もう一枚の写真には長い沈黙を経て、ラジオ放送に臨む女性アナウンサーの堂々たる姿もあった。あたかも突然氷が溶け始めてアフガンの戦禍に終止符が打たれようとしているかのように見える。だがこれが束の間の幻でないことを祈りたい。 実際のところ、所謂「テロリスト」とアメリカとの新型戦争が今後どのように展開するのかは誰にも予測できない。この間、老いも若きも女達は一体どこへ姿を消してしまったのだろうと思っていた。ブルカの下の彼女たちの実像を目撃する機会はなかった。そして子ども達はどうしているのだろう。「国際難民救援組織」によれば、推定140,000人の「目に見える」、つまり難民認定を受けた人々がパキスタンの難民キャンプに暮らしている一方、最近の戦でアフガニスタン領内の住処を失い、閉鎖された国境を突破してパキスタンに入り込んだ「目に見えない」、すなわち難民認定を受けていない人々が135,000人はいるということだ。 「おんなこども」のいない世界には活気がない。そして住処のないおんなこども(実は男も)は、とりわけこれからの季節には、痛ましい。情緒や感性の表現を抑圧されたところに本当の命はない。その国の日常生活を圧殺したのは何ものだろう。長い年月をかけて培われた伝統、習慣、幾多の習わしがそう容易く現代の戦で消滅するわけがないとは思う。女達は必ずどんな状況下でもそれらを維持していくに違いない。だがやはり、援助は要る。それが他国に科せられた最大の課題だ。誰も当事者の意に反した干渉をすることは許されないけれども。 世界中の女達が一様であれとは思わない。それぞれのやり方で生活を立てていければよい。但し、「伝統」に名を借りた悪しき因習は、「伝統、風習」とは別物だ。暴力から解き放たれたところでのみ、女達は花開く。男達も目に見える戦ばかりでなく、内的な戦から、女達の元へ帰ってこられないものだろうか。 笑顔の女達は美しい。人間的な尊厳と品位に満ちた笑顔を、もしかすると日本の女達の多くが、忙しさに追われるうちにどこかへ置き忘れてきたかも知れない。深い情緒に溢れた笑顔を取り戻さなくてはならないのは、我々の方だったろうか。人と暮らしを慈しむ笑顔。幾枚かの小さな新聞写真に触発されて、もうすぐ東京の会場で開かれる写真展『アフガンの女性と子ども達』を学生と一緒に見に行くことになった。もっと沢山の美しい人々に出会えるような気がする。
|
|
10/6 (土), 2001 メール友達の一人から便りが届いた。長い間ベッドで生活している人。彼は詩人だ。最近急病で入院を余儀なくされたという。入院中はテレビもラジオも新聞も、ましてやパソコンに触れることもかなわなかった。にもかかわらず、淡々とした筆致で「そのようなものから少し離れてみるのも良いものです」と。私は彼の心根に深く感ずるものがあった。それほどの困難からどうやって斯くも清明な境地を得たのだろう。長いメールの最後に「三行日記が更新されるのを期待しています」という言葉。私は恥じ入る。いつまでも自分の痛みに耽溺しているのが如何に愚かなことか気づかずにはいられない。何が起ころうとも人生は続いていく。 まだしばらく「三行日記」は再開できない。でもその代わり、「情景描写」という新ページを日英両語で開設してみようと思う。不定期更新、長さにも制限なしの気ままなページとしておこう。「エッセイ」と呼ぶには短すぎる、メモ程度のもの。格好は悪いがそこで思うこと感じることを解き放ってみたい。私の内面の情景と外界の情景をともに観察したスケッチというほどのつもりで「情景描写」。 人は書かずにいられないから書く。それだけが書く理由になる。技法はその欲求にあとからついてくる。負の力であろうと正の力であろうと、書きたい気持ちは止められない。友人に感謝している。何を躊躇うのかと背中を押された気がする。「三行日記」再開まで、暫くここで書いていよう。彼の目に触れると良いが。 掛け値なしに、書くことには喜びがある。読み手がいてくれる幸せもある。ウェッブが誰にも等しく自由にものを書く場であり続けてくれることを祈る。サイバーテロや「検閲」を何としても阻まなくてはならない。書き続けることによってのみ、我々の声がこの世に響くならば。私も書かせて貰いたい。
|
back to Top of this page
Back to
Home